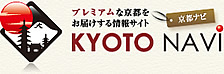- 京都観光 京都ナビ
- 面白い京都には発見がいっぱい!
グルメ
![]()
![]()
 昔はよその家におよばれをした時、料理は全部食べずに、少し残す程度が良いとされていました。
昔はよその家におよばれをした時、料理は全部食べずに、少し残す程度が良いとされていました。一般には全部きれいに残さず食べる事が大切と教えられてきたのにと思われがちですが、全部食べてしまうと、
それを出していただいた家の人に、物足りなかったのかという心配をかけるからだそうです。京都では、少し残す事で、暗に十分頂きましたという風習があります。
![]()
 8月16日の五山の送り火(大文字焼き)で、杯やお盆に大文字の「大」を写して飲むと、無病息災や中風にならないといわれています。その他に「茄子に穴をあけて大文字を見ると目を患わない」とか「送り火の燃え木の炭は、家の魔よけになる」 「消し炭を粉にして飲むと胃薬になる」などの言いつたえがあります。
8月16日の五山の送り火(大文字焼き)で、杯やお盆に大文字の「大」を写して飲むと、無病息災や中風にならないといわれています。その他に「茄子に穴をあけて大文字を見ると目を患わない」とか「送り火の燃え木の炭は、家の魔よけになる」 「消し炭を粉にして飲むと胃薬になる」などの言いつたえがあります。そのためか今でも送り火の翌朝は、燃木を拾う人で早朝より山に登る人が多くいます。
![]()
 一説に敷居は人の頭を表すともいい、表の敷居は父、裏の敷居は母、中の敷居は子とされ、その敷居を踏む、つまり、人の頭を踏むと言うような行為をするということは、出世できないと伝えられ、家の敷居を踏んではいけないと言われています。
一説に敷居は人の頭を表すともいい、表の敷居は父、裏の敷居は母、中の敷居は子とされ、その敷居を踏む、つまり、人の頭を踏むと言うような行為をするということは、出世できないと伝えられ、家の敷居を踏んではいけないと言われています。
![]()
 一条戻り橋は、堀川通沿いを流れる堀川に架かる小さな橋。平安時代、文章博士三善清行が没したことを聞いた子の葬列に出くわし、棺にすがって泣き崩れると、父が一時よみがえった事から、「戻り橋」と呼ぶようになったと伝えられています。
一条戻り橋は、堀川通沿いを流れる堀川に架かる小さな橋。平安時代、文章博士三善清行が没したことを聞いた子の葬列に出くわし、棺にすがって泣き崩れると、父が一時よみがえった事から、「戻り橋」と呼ぶようになったと伝えられています。「戻り」にこだわり、嫁いだ先から戻ってこないようにと、婚礼時には橋を渡らないように遠回りをする風習もあります。
![]()
 京都の人は、お葬式や霊柩車に出会うと、握りこぶしの中に親指を入れて隠す事もあります。親指は自分の親に通じ、親を死から遠ざける為に親指を隠すといわれています。
京都の人は、お葬式や霊柩車に出会うと、握りこぶしの中に親指を入れて隠す事もあります。親指は自分の親に通じ、親を死から遠ざける為に親指を隠すといわれています。
![]()
![]()
京都タワーの外観はろうそくを模したものだという説が一般的ですが、実は設計者のイメージは灯台です。京都タワーの社史には設計初期段階のデザイン画が掲載されています。その姿は和歌山県の潮岬灯台をモデルにしたとしています。京都 タワーの高さは131m。この数字は、設計当時の京都市の人口・131万人にちなむという説もあるそうです。建設計画の大要が決まったとされる昭和37年12月ごろの人口は131万人台だったそうです。



京ことばとは、大きく町方のことばと御所ことばに分かれる。町方のことばとしては西陣の職人ことば(織屋関係のことば)、中京ことば(問屋を中心とした商屋で用いることば)、花街ことば(祇園など花街特有の接客ことば)、そして農家ことばと、4つに分かれる。
優雅なことばとして日本全国に広く知られ、母音を長く丁寧に発音して発音のテンポが遅い点や、柔らかく角の立たない言い回しを好み、敬語や婉曲表現を多用する点が女性的であり、そのことが優雅性の要因であるとしている。
京ことばは、人をやさしくしてくれる独特のニュアンスがあります。
優雅なことばとして日本全国に広く知られ、母音を長く丁寧に発音して発音のテンポが遅い点や、柔らかく角の立たない言い回しを好み、敬語や婉曲表現を多用する点が女性的であり、そのことが優雅性の要因であるとしている。
京ことばは、人をやさしくしてくれる独特のニュアンスがあります。
![]()